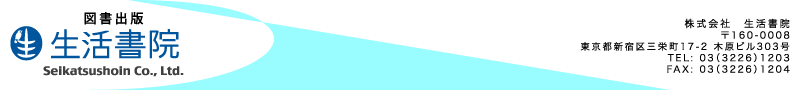
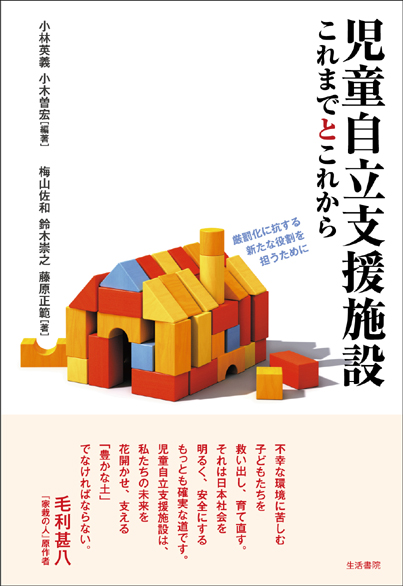
児童自立支援施設これまでとこれから
──厳罰化に抗する新たな役割を担うために
四六判並製 272頁 2000円 ISBN 978-4-903690-42-1
(書影拡大)
「感化院」「教護院」時代からの「非行児童」処遇の優れた実践の歴史の一方、定員割れが続き子どもたちに「利用されぬ施設」と化している現状、それでもなお、子どもたちの福祉と発達のために絶対に必要な場としての責任と未来。全国に58ヶ所、約2,000人の子どもが生活する、児童自立支援施設のこれまでを振り返り、向かうべき新たな方向性を明らかにする。
まえがき 小林英義
序章 児童自立支援施設の概要 小林英義
1 子どもの声を世の人々に
2 施設の概要
3 入所理由とその背景
第1章 児童自立支援施設、その独自性と実践 梅山佐和
はじめに
1 多様な児童自立支援施設
1−1 岡山県立成徳学校
1−2 広島県立広島学園
1−3 東京都立萩山実務学校
2 ある日の風景
3 子どもたちへのまなざし――"育ちに寄り添う"おとなの存在
4 変化への挑み
おわりに
第2章 教護院からの伝承と改革 鈴木崇之
はじめに
1 「教護院」誕生以前
2 「教護院」の時代
3 「教護院」の処遇理念の変遷
4 「教護院」から「児童自立支援施設」への「改革」
5 「教護院」からのバトンタッチは成功したのか
6 「受け継ぐこと」と「改善すること」――まとめにかえて
第3章 司法と福祉の連携――日本司法福祉学会での過去8年間の取り組みから 小林英義
1 日本司法福祉学会の設立趣旨
2 分科会の企画
3 日本司法福祉学会での分科会討議
3−1 第3回(大阪)大会(2002年8月4日)
3−2 第5回(千葉)大会(2004年8月8日)
3−3 第6回(京都)大会(2005年8月7日)
3−4 第7回(三重)大会(2006年8月6日)
3−5 第8回(大阪)大会(2007年8月5日)
3−6 第9回(福岡)大会(2008年8月3日)
4 愛知学園事件に係る分科会
5 今後の課題
6 司法と福祉の連携
第4章 児童自立支援施設の担い手論 藤原正範
1 担い手論を論ずるにあたって――寮長の退職とA子
2 何が問題なのか
3 児童自立支援施設職員の資格要件
4 資質論の変遷
5 担い手の検討
6 児童福祉施設最低基準の改正
7 児童自立支援施設の担い手はどうあるべきか
7−1 担い手を論ずる上での前提条件
7−2 夫婦制と公務員であること
7−3 一路白頭ニ到ル
7−4 再度、期待される担い手の条件
第5章 改めて、児童自立支援施設に問われているものとは何か
――「児童自立支援施設のあり方検討会」報告を中心として 小木曽宏
はじめに
1 少年法改正の議論と児童自立支援施設の位置づけ
2 少年法改正に活かされなかった議論
3 措置は適正に行われているか
4 少年法改正と児童相談所、児童自立支援施設に向けられた批判
5 「児童自立支援施設のあり方に関する研究会」設置の経緯
6 「児童自立支援施設のあり方に関する研究会」報告書とは
6−1 「基本的な考え方」について 6−2 自立支援機能の充実・強化を図る
7 児童自立支援施設の可能性と未来
資料編 小林英義
〈資料1〉第3回(大阪)大会
〈資料2〉第5回(千葉)大会
〈資料3〉第6回(京都)大会
〈資料4〉第7回(三重)大会
〈資料5〉第8回(大阪)大会
〈資料6〉第9回(福岡)大会
あとがき 小木曽宏