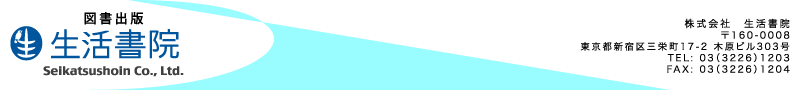
【Web連載】
家で死ぬ本──『生死本』(仮)の準備・2
立岩 真也
(2012/08/21)
◆1・2・…
◆文献表(作成中)
*このごろのことについては「安楽死・尊厳死 2012」等でお知らせすることにして、本の紹介のための本のための補足のための草稿を前回から掲載させていただいている。
「家で死ぬ」、といった題をもつ本がたくさんある。それと対にされる──というのは正確ではなく、「ホスピス」が対置されることもあり、さらに「在宅ホスピス」といった言葉も現われる──「病院で死ぬこと」系の本とともに、出版年順にいくつかをあげる。なお「脱病院」の本で最も知られているのはイリイチの『脱病院化社会──医療の限界』(Illich[1976=1979])ということになるだろうが、この本は近代医療全般を批判する本で、原題は「Medical Nemesis:The Expropriation of Health」で、「(脱)病院」の語は入っていない。
・『家で死ぬ──柳原病院における在宅老人看護の10年』(大沼和加子・佐藤陽子[1989])、
・『病院で死ぬということ』(山崎章郎[1990] )
・『家庭で看取る癌患者──在宅ホスピス入門』(川越厚編[1991]、著者は医師)
・『家で死にたい──家族と看とったガン患者の記録』(川越厚[1992])
・『やすらかな死──癌との闘い・在宅の記録』(川越厚編[1994])
・『続・病院で死ぬということ──そして今、僕はホスピスに』(山崎章郎[1994])
・『家に帰りたい! 家で死にたい!──在宅ホスピス8つのケース』(小笠原一夫・吉原清児[1994])
・『家で死ぬということ──がんの痛みからの解放』(山室誠[1995])
・『みんな、家で死にたいんだに』(網野皓之[1996])
・『最期まで家にいられる在宅ケア──東京・千住地域の巡回型24時間在宅ケアの実践』(増子忠道・宮崎和加子編[1996])
・『人は家で死ぬべきだ──在宅介護の日々』(浅野由美子[1997])、
・『人間らしく死にたい!──在宅死を見つめて20年』(鈴木荘一[1998])
・『家で死ぬのはわがままですか──訪問看護婦が20年実践した介護の現場から』(宮崎和加子[1998])
・『きらきら光る最期のとき──在宅ホスピス日誌』(西山照恵[1998])
・『たかね先生の在宅介護論──地域で老いて家で死ぬ』(矢嶋嶺[2000])
・『在宅死の歴史──近代日本のターミナルケア』(新村拓[2001]──地主の日記等から日本近代の見取りの様子を記している)、
・『在宅死──豊かな生命の選択』(玉地任子[2001])
・『死にゆく患者のメッセージ──訪米医学研修生と在宅ホスピスの人々』(南吉一編[2001])
・『「家で死ぬ」ということ──家族が後悔しない身内の介護と看取り方』(西村文夫・宮原伸二[2002])、
・『笑顔で「さよなら」を──在宅ホスピス医の日記から』(内藤いづみ[2002])
・『あなたが、いてくれる。──在宅ホスピス医いのちのメッセージ』(内藤いづみ[2005])、
・『病院で死なないという選択──在宅・ホスピスを選んだ家族たち』(中山あゆみ[2005]、著者はジャーナリスト)
・『家で看取るということ──末期がん患者をケアする在宅ホスピスの真実』(川越厚・川越博美[2005])
・『自宅で死にたい──老人往診3万回の医師が見つめる命』(川人明[2005])
・『在宅ホスピスのススメ──看取りの場を通したコミュニティの再生へ』(二ノ坂保喜監修[2005]、監修者・著者は医師、看護師等)
・『自宅で迎える幸せな最期』(押川真喜子[2005]、著者は聖路加国際病院訪問看護科ナースマネージャー)
・『あなたが、いてくれる。──在宅ホスピス医いのちのメッセージ』(内藤いづみ[2005]、著者は医師)
・『病院で死なないという選択──在宅・ホスピスを選んだ家族たち』(中山あゆみ[2005])
・『在宅での看取りのケア──家族支援を中心に』(宮崎和加子監修[2006])
・『家で死ぬための医療とケア──在宅看取り学の実践』(新田國夫編[2007])
・『理想の在宅死と現実の在宅死』(赤座良香[2007]、著者は看護師)
・『やっぱり、家で死にたいんだ──都市の在宅医療12年』(網野皓之[2008])
・『最期の流儀──ガン患者にみる在宅終末期緩和ケアの現実と希望』(種山千邦[2008])
中で最も話題になったのは『病院で死ぬということ』(山崎章郎[1990])だろう。(私も非常勤の大学のゼミ──日本社会事業大学の新入生ゼミといったものだった──で、学生のリクエストがあって、この本をみなで読んだ記憶がある)。(山崎はその後、東京の桜町ホスピスの運営に関わる。『ここが僕たちのホスピス』(山崎[1993b])、『がんの苦しみが消える──ホスピス・緩和ケア病棟ガイド』(山崎[1994])等、関連文献は別に紹介する。)
hp「施設/脱施設」で文献などいろいろ紹介しているが、日本での身体障害者の脱施設の主張についてはまず『生の技法』(安積他[1990][1995][2012])所収の尾中[1990]。一九七〇年に始まる「府中療育センター闘争」が最初のものと言ってよいと思うが、それに関わり後に後にそこを出た人が書いた本として『抵抗の証 私は人形じゃない』(三井絹子[2006]、七二年の『朝日ジャーナル』に掲載された「わたしたちは人形じゃない──新田絹子さんの手記」(三井(旧姓:新田[1972]はhpに全文を収録)、『足文字は叫ぶ!──全身性障害のいのちの保障を』(新田編[2009])。一九七六年の「和歌山県立身体障害者福祉センター糾弾占拠闘争」については『関西障害者運動の現代史──大阪青い芝の会を中心に』(定藤[2011:154-168])。
それ以前には、 二〇世紀初頭から児童施設について、そこに育つ子どもの身体への影響、次に心理的な影響を「ホスピタリズム」として問題にされた。『社会福祉学の「科学」性──ソーシャルワーカーは専門職か?』(三島[2007])でホスピタリズムを巡る言説について紹介されている。
そして知的障害の人たちに関って出てきた「ノーラマイゼーション」がある。『現代倫理学事典』の「ノーラマイゼーション」の項目(四〇〇字・以下全文)では次のように記した(より長い文章としてはは『生命倫理とは何か』(市野川編[2002])に収録されている「ノーラマイゼーション」(立岩[20020822]))。
「一九五〇年代のデンマークで、巨大な収容施設での知的障害者の暮らせられ方を親たちが批判し、バンク=ミケルセンがそれを支持して登場した。一九六〇年代以降スウェーデン他に波及し、国際的に普及した。もとの語の読みを継いでノーマリゼーションと読まれることもある。障害者に、普通の市民の通常の生活状態を提供することを目的に掲げる。日本では一九七〇年代に使われ始め、一九八一年の国際障害者年の前後からよく知られる言葉になった。この語は、初期には施設での生活は前提とした上でその小規模化とその中での生活の諸条件の改善を目指したが、後には自立生活運動の流れも受けて脱施設を射程に入れるものとなった。しかし日本の一九七〇年代以降はむしろ施設が作られていく時期であり、施設をどうするかという具体的で厳しい論点をおおむね回避しつつ、普通にするという穏当な語感がよかったのか、表立っては誰にも反対されることのない言葉として普及することになった。」(立岩[20061215])
ここで一つ押さえておいた方がよいことを加えと、この知的障害者の施設にしても次にあげる精神病院にしても、ヨーロッパや北米にあったのは本当に巨大な施設・コロニーであったということであり、それは日本で、当初民間で、ぽつりぼつりとようやくできたいった施設とは──どちらがましだといったことを言いたいのはではないが──様子がだいぶ異なるものだった(米国での歴史を記した『「精神薄弱」の誕生と変貌──アメリカにおける精神遅滞の歴史』(Trent[1994=1997])等が参考になる)。
そして精神病院の「脱病院化」の動きがあった。精神医療の「改革」については別の本を用意するので──日本の場合、他の障害者施設と異なる背景から、省くものを省きなどすれば)経営的に成り立つ民間病院としての精神病院がとくに一九六〇年代に増加する事情も含め──ここでは省く。ただ病院・施設にいたくないとしても、代わりにもっとよい場所がなければ、当たり前のことだが、まだそこにいた方がましである。しかし代わりにいる場所がないまま「脱」が進められたことがあった。一九六〇年代の米国における精神障害者の「脱施設(病院)化」が、暮らしやすい居場所を見つけられない人たちを大量にを生み出したことはよく知られている。中井久夫の『徴候・記憶・外傷』より。
「アメリカにとって一九六〇年代は力動精神医学が中心でしたが、ケネディ大統領は、精神病院の病床を五十万床から十五万床に減らすことを一気に三年で行います。大統領の任期が四年ですから二十年計画でやるとういことはアメリカではあり得ません。精神病院を小さくする代わりに各地に精神保健センターをつくるという計画でした。しかし精神保健センターには患者さんは来ませんでした。カーター夫人が一九七七年に世界精神保健連盟(WFMH)の総会で、これは失敗であり、患者はセンターに来なかったということを話していました。実際、大部分がホームレスになったり、あるいはギャングに生活保護費のウワマエをハネられる存在になったといいます。<0129<
現在アメリカではどうなっているかというと、メンタルヘルスセンターはとうとうレーガン大統領の時代には廃止されてしまったということです。」(中井[2004:129-130])
この時期、病院・病床を増やすことを支持していた日本の精神科医が「ケネディ教書」をどう受け止めたのか、やがていつのまにか違うことを言うことになったのか等については三野宏治が調べを始めている(三野[2010][PDF])。
それから二〇年弱たって、「家で死ぬ」方向の本がたくさん出される。まずそれはうるわしいこととして語られる。それはもっともなことではある。病院は居づらいところで、仮にその環境他がかなりよくなったとしても、それでもそうよいものではない。その主張はもっともなことだ。またそれは「精神病院」批判と同じ時期なされた「(悪徳)老人病院」批判(『唯の生』(立岩[20090325])の第3章「有限でもあるから控えることについて──その時代に起こったこと」の2節1「老人病院批判」で紹介した。)
ただ、そのころになると、あるいはすこし遅れて、日本でも「在宅へ」は既に政策の標語になっている。その方向への「誘導」がなされるようになって久しい。
それは、実際には、もう誰もが知っているように、まだいたいのだが、あるいはいざるをえないのだが、一つに、病院から病院、病院から施設、へと漂流する人々を生み出した。そしてもう一つ、家に戻ることになる人が出てきた。結果、一つに、に介助(介護)が家族に戻ってきた。一つに、福祉施設、在宅の生活では医療を受けにくいことになった。 福祉施設でできない、それでおしまいということがある。自宅に戻って終わりという人もいる。そんなことはない、在宅でも相当のことができると言い、実践する人もいるが(川島孝一郎について上掲拙著(立岩[20090325:271-272]で言及)、しばしば医療他を得ないことと在宅(死)とはセットにされて語られる。私は、後者(住みたいところに住むこと)が優先されてよいことがあることを認める。しかし現実にしばしば生じているのは、両方が欲しいのだが、前者を得ると後者が得られないこと、後者が得られないまま「戻される」「送られる」ことである。
それでもよい、それがよいとするか、そうでないか。多くの人は現在の転院・退院の強要をひどいことだとは考えている。考える前に、体験している。そして不満を言う。二〇〇〇年代の後半以降、「医療崩壊」がおおいに語られる(これも別途紹介する)。ただ、(「濃厚な」)医療についてはどうか。それは(技術的に在宅で可能であったも)いらないとする人もいる。ただ、余計なことをしてほしくないのはそのとおりだとして、例えば「胃ろう」はどうということのない簡単な仕掛けでしかなく、すくなくとも高度でも侵襲的でもなく──普通の意味では──医療でもない。このことに関わる文献もまた紹介する。


■上記とひとまずべつに、私たち?が関わった生活書院の本・2(新しいものから3つずつぐらい)
◆立岩 真也・村上 潔 20111205 『家族性分業論前哨』,生活書院,360p. ISBN-10: 4903690865 ISBN-13: 978-4903690865 2200+110 [amazon]/[kinokuniya] ※ w02, f04
◆立命館大学生存学研究センター 編 20110525 『生存学』Vol.4,生活書院,251p. ISBN-10: 4903690768 ISBN-13: 9784903690766 2200+110 [amazon]/[kinokuniya] ※
◆安部 彰 20110331 『連帯の挨拶──ローティと希望の思想』,生活書院,328p. ISBN-10: 490369075X ISBN-13: 978-4903690759 \2940 [amazon]/[kinokuniya] ※



家で死ぬ本──『生死本』(仮)の準備・2
立岩 真也
(2012/08/21)
◆1・2・…
◆文献表(作成中)
*このごろのことについては「安楽死・尊厳死 2012」等でお知らせすることにして、本の紹介のための本のための補足のための草稿を前回から掲載させていただいている。
「家で死ぬ」、といった題をもつ本がたくさんある。それと対にされる──というのは正確ではなく、「ホスピス」が対置されることもあり、さらに「在宅ホスピス」といった言葉も現われる──「病院で死ぬこと」系の本とともに、出版年順にいくつかをあげる。なお「脱病院」の本で最も知られているのはイリイチの『脱病院化社会──医療の限界』(Illich[1976=1979])ということになるだろうが、この本は近代医療全般を批判する本で、原題は「Medical Nemesis:The Expropriation of Health」で、「(脱)病院」の語は入っていない。
・『家で死ぬ──柳原病院における在宅老人看護の10年』(大沼和加子・佐藤陽子[1989])、
・『病院で死ぬということ』(山崎章郎[1990] )
・『家庭で看取る癌患者──在宅ホスピス入門』(川越厚編[1991]、著者は医師)
・『家で死にたい──家族と看とったガン患者の記録』(川越厚[1992])
・『やすらかな死──癌との闘い・在宅の記録』(川越厚編[1994])
・『続・病院で死ぬということ──そして今、僕はホスピスに』(山崎章郎[1994])
・『家に帰りたい! 家で死にたい!──在宅ホスピス8つのケース』(小笠原一夫・吉原清児[1994])
・『家で死ぬということ──がんの痛みからの解放』(山室誠[1995])
・『みんな、家で死にたいんだに』(網野皓之[1996])
・『最期まで家にいられる在宅ケア──東京・千住地域の巡回型24時間在宅ケアの実践』(増子忠道・宮崎和加子編[1996])
・『人は家で死ぬべきだ──在宅介護の日々』(浅野由美子[1997])、
・『人間らしく死にたい!──在宅死を見つめて20年』(鈴木荘一[1998])
・『家で死ぬのはわがままですか──訪問看護婦が20年実践した介護の現場から』(宮崎和加子[1998])
・『きらきら光る最期のとき──在宅ホスピス日誌』(西山照恵[1998])
・『たかね先生の在宅介護論──地域で老いて家で死ぬ』(矢嶋嶺[2000])
・『在宅死の歴史──近代日本のターミナルケア』(新村拓[2001]──地主の日記等から日本近代の見取りの様子を記している)、
・『在宅死──豊かな生命の選択』(玉地任子[2001])
・『死にゆく患者のメッセージ──訪米医学研修生と在宅ホスピスの人々』(南吉一編[2001])
・『「家で死ぬ」ということ──家族が後悔しない身内の介護と看取り方』(西村文夫・宮原伸二[2002])、
・『笑顔で「さよなら」を──在宅ホスピス医の日記から』(内藤いづみ[2002])
・『あなたが、いてくれる。──在宅ホスピス医いのちのメッセージ』(内藤いづみ[2005])、
・『病院で死なないという選択──在宅・ホスピスを選んだ家族たち』(中山あゆみ[2005]、著者はジャーナリスト)
・『家で看取るということ──末期がん患者をケアする在宅ホスピスの真実』(川越厚・川越博美[2005])
・『自宅で死にたい──老人往診3万回の医師が見つめる命』(川人明[2005])
・『在宅ホスピスのススメ──看取りの場を通したコミュニティの再生へ』(二ノ坂保喜監修[2005]、監修者・著者は医師、看護師等)
・『自宅で迎える幸せな最期』(押川真喜子[2005]、著者は聖路加国際病院訪問看護科ナースマネージャー)
・『あなたが、いてくれる。──在宅ホスピス医いのちのメッセージ』(内藤いづみ[2005]、著者は医師)
・『病院で死なないという選択──在宅・ホスピスを選んだ家族たち』(中山あゆみ[2005])
・『在宅での看取りのケア──家族支援を中心に』(宮崎和加子監修[2006])
・『家で死ぬための医療とケア──在宅看取り学の実践』(新田國夫編[2007])
・『理想の在宅死と現実の在宅死』(赤座良香[2007]、著者は看護師)
・『やっぱり、家で死にたいんだ──都市の在宅医療12年』(網野皓之[2008])
・『最期の流儀──ガン患者にみる在宅終末期緩和ケアの現実と希望』(種山千邦[2008])
中で最も話題になったのは『病院で死ぬということ』(山崎章郎[1990])だろう。(私も非常勤の大学のゼミ──日本社会事業大学の新入生ゼミといったものだった──で、学生のリクエストがあって、この本をみなで読んだ記憶がある)。(山崎はその後、東京の桜町ホスピスの運営に関わる。『ここが僕たちのホスピス』(山崎[1993b])、『がんの苦しみが消える──ホスピス・緩和ケア病棟ガイド』(山崎[1994])等、関連文献は別に紹介する。)
hp「施設/脱施設」で文献などいろいろ紹介しているが、日本での身体障害者の脱施設の主張についてはまず『生の技法』(安積他[1990][1995][2012])所収の尾中[1990]。一九七〇年に始まる「府中療育センター闘争」が最初のものと言ってよいと思うが、それに関わり後に後にそこを出た人が書いた本として『抵抗の証 私は人形じゃない』(三井絹子[2006]、七二年の『朝日ジャーナル』に掲載された「わたしたちは人形じゃない──新田絹子さんの手記」(三井(旧姓:新田[1972]はhpに全文を収録)、『足文字は叫ぶ!──全身性障害のいのちの保障を』(新田編[2009])。一九七六年の「和歌山県立身体障害者福祉センター糾弾占拠闘争」については『関西障害者運動の現代史──大阪青い芝の会を中心に』(定藤[2011:154-168])。
それ以前には、 二〇世紀初頭から児童施設について、そこに育つ子どもの身体への影響、次に心理的な影響を「ホスピタリズム」として問題にされた。『社会福祉学の「科学」性──ソーシャルワーカーは専門職か?』(三島[2007])でホスピタリズムを巡る言説について紹介されている。
そして知的障害の人たちに関って出てきた「ノーラマイゼーション」がある。『現代倫理学事典』の「ノーラマイゼーション」の項目(四〇〇字・以下全文)では次のように記した(より長い文章としてはは『生命倫理とは何か』(市野川編[2002])に収録されている「ノーラマイゼーション」(立岩[20020822]))。
「一九五〇年代のデンマークで、巨大な収容施設での知的障害者の暮らせられ方を親たちが批判し、バンク=ミケルセンがそれを支持して登場した。一九六〇年代以降スウェーデン他に波及し、国際的に普及した。もとの語の読みを継いでノーマリゼーションと読まれることもある。障害者に、普通の市民の通常の生活状態を提供することを目的に掲げる。日本では一九七〇年代に使われ始め、一九八一年の国際障害者年の前後からよく知られる言葉になった。この語は、初期には施設での生活は前提とした上でその小規模化とその中での生活の諸条件の改善を目指したが、後には自立生活運動の流れも受けて脱施設を射程に入れるものとなった。しかし日本の一九七〇年代以降はむしろ施設が作られていく時期であり、施設をどうするかという具体的で厳しい論点をおおむね回避しつつ、普通にするという穏当な語感がよかったのか、表立っては誰にも反対されることのない言葉として普及することになった。」(立岩[20061215])
ここで一つ押さえておいた方がよいことを加えと、この知的障害者の施設にしても次にあげる精神病院にしても、ヨーロッパや北米にあったのは本当に巨大な施設・コロニーであったということであり、それは日本で、当初民間で、ぽつりぼつりとようやくできたいった施設とは──どちらがましだといったことを言いたいのはではないが──様子がだいぶ異なるものだった(米国での歴史を記した『「精神薄弱」の誕生と変貌──アメリカにおける精神遅滞の歴史』(Trent[1994=1997])等が参考になる)。
そして精神病院の「脱病院化」の動きがあった。精神医療の「改革」については別の本を用意するので──日本の場合、他の障害者施設と異なる背景から、省くものを省きなどすれば)経営的に成り立つ民間病院としての精神病院がとくに一九六〇年代に増加する事情も含め──ここでは省く。ただ病院・施設にいたくないとしても、代わりにもっとよい場所がなければ、当たり前のことだが、まだそこにいた方がましである。しかし代わりにいる場所がないまま「脱」が進められたことがあった。一九六〇年代の米国における精神障害者の「脱施設(病院)化」が、暮らしやすい居場所を見つけられない人たちを大量にを生み出したことはよく知られている。中井久夫の『徴候・記憶・外傷』より。
「アメリカにとって一九六〇年代は力動精神医学が中心でしたが、ケネディ大統領は、精神病院の病床を五十万床から十五万床に減らすことを一気に三年で行います。大統領の任期が四年ですから二十年計画でやるとういことはアメリカではあり得ません。精神病院を小さくする代わりに各地に精神保健センターをつくるという計画でした。しかし精神保健センターには患者さんは来ませんでした。カーター夫人が一九七七年に世界精神保健連盟(WFMH)の総会で、これは失敗であり、患者はセンターに来なかったということを話していました。実際、大部分がホームレスになったり、あるいはギャングに生活保護費のウワマエをハネられる存在になったといいます。<0129<
現在アメリカではどうなっているかというと、メンタルヘルスセンターはとうとうレーガン大統領の時代には廃止されてしまったということです。」(中井[2004:129-130])
この時期、病院・病床を増やすことを支持していた日本の精神科医が「ケネディ教書」をどう受け止めたのか、やがていつのまにか違うことを言うことになったのか等については三野宏治が調べを始めている(三野[2010][PDF])。
それから二〇年弱たって、「家で死ぬ」方向の本がたくさん出される。まずそれはうるわしいこととして語られる。それはもっともなことではある。病院は居づらいところで、仮にその環境他がかなりよくなったとしても、それでもそうよいものではない。その主張はもっともなことだ。またそれは「精神病院」批判と同じ時期なされた「(悪徳)老人病院」批判(『唯の生』(立岩[20090325])の第3章「有限でもあるから控えることについて──その時代に起こったこと」の2節1「老人病院批判」で紹介した。)
ただ、そのころになると、あるいはすこし遅れて、日本でも「在宅へ」は既に政策の標語になっている。その方向への「誘導」がなされるようになって久しい。
それは、実際には、もう誰もが知っているように、まだいたいのだが、あるいはいざるをえないのだが、一つに、病院から病院、病院から施設、へと漂流する人々を生み出した。そしてもう一つ、家に戻ることになる人が出てきた。結果、一つに、に介助(介護)が家族に戻ってきた。一つに、福祉施設、在宅の生活では医療を受けにくいことになった。 福祉施設でできない、それでおしまいということがある。自宅に戻って終わりという人もいる。そんなことはない、在宅でも相当のことができると言い、実践する人もいるが(川島孝一郎について上掲拙著(立岩[20090325:271-272]で言及)、しばしば医療他を得ないことと在宅(死)とはセットにされて語られる。私は、後者(住みたいところに住むこと)が優先されてよいことがあることを認める。しかし現実にしばしば生じているのは、両方が欲しいのだが、前者を得ると後者が得られないこと、後者が得られないまま「戻される」「送られる」ことである。
それでもよい、それがよいとするか、そうでないか。多くの人は現在の転院・退院の強要をひどいことだとは考えている。考える前に、体験している。そして不満を言う。二〇〇〇年代の後半以降、「医療崩壊」がおおいに語られる(これも別途紹介する)。ただ、(「濃厚な」)医療についてはどうか。それは(技術的に在宅で可能であったも)いらないとする人もいる。ただ、余計なことをしてほしくないのはそのとおりだとして、例えば「胃ろう」はどうということのない簡単な仕掛けでしかなく、すくなくとも高度でも侵襲的でもなく──普通の意味では──医療でもない。このことに関わる文献もまた紹介する。


■上記とひとまずべつに、私たち?が関わった生活書院の本・2(新しいものから3つずつぐらい)
◆立岩 真也・村上 潔 20111205 『家族性分業論前哨』,生活書院,360p. ISBN-10: 4903690865 ISBN-13: 978-4903690865 2200+110 [amazon]/[kinokuniya] ※ w02, f04
◆立命館大学生存学研究センター 編 20110525 『生存学』Vol.4,生活書院,251p. ISBN-10: 4903690768 ISBN-13: 9784903690766 2200+110 [amazon]/[kinokuniya] ※
◆安部 彰 20110331 『連帯の挨拶──ローティと希望の思想』,生活書院,328p. ISBN-10: 490369075X ISBN-13: 978-4903690759 \2940 [amazon]/[kinokuniya] ※



UP:20120814 REV: